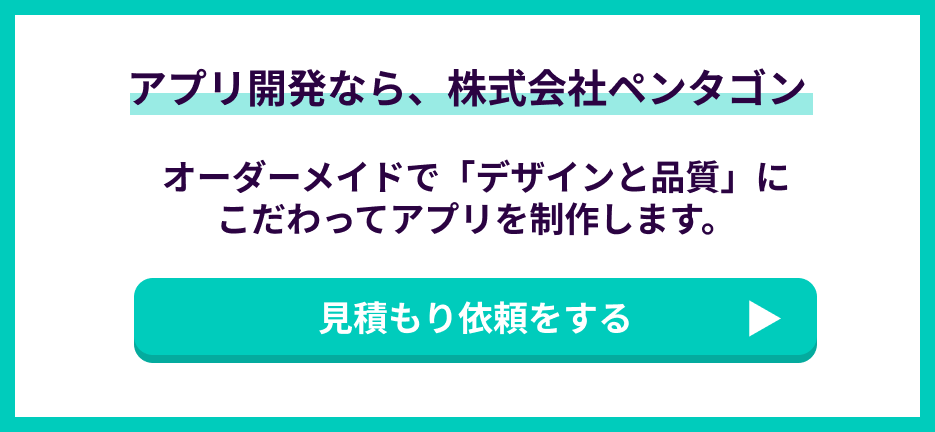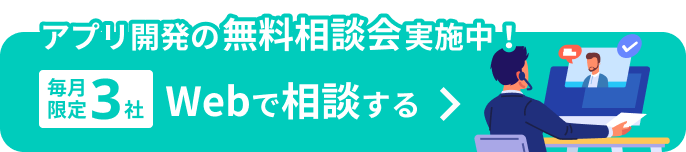アプリ担当必見「アプリグロース」を実現する9つの施策解説
アプリのグロースとは、主に以下の3つの視点に分かれます
- ユーザーの獲得
- ユーザーの維持
- 収益の最大化
この3つの項目を継続的に改善し続けることでアプリは成長を続けます。
これらは単独で進めるのではなく、相互に関連し合っています。たとえば、多額の広告費を投じてユーザーを獲得しても、維持施策が不十分であれば短期間で離脱が進み、結果として収益の最大化にはつながりません。一方で、既存ユーザーのエンゲージメントを高め、継続利用を促すことができれば、広告費を抑えながらLTV(顧客生涯価値)を向上させ、収益性の高い運営が実現できます。
そのため、アプリのグロース戦略を考える際には、
「どのチャネルからどのようにユーザーを呼び込むか」
「獲得したユーザーにどう価値を感じてもらい、定着させるか」
「継続利用を前提に、どのタイミングで収益化を図るか」
といった全体像を見渡した設計が欠かせません。単発のキャンペーンや機能改善に留まらず、長期的な改善サイクルを構築することこそが、真のグロースに直結します。
本記事では、アプリ開発会社の株式会社ペンタゴンで代表を務める筆者が、アプリのグロース戦略の基本から具体的な実践方法まで、成功事例を交えて詳しく解説していきます。
ちなみに、当社では数々のアプリ開発・運用実績があり、大手人材紹介会社の転職アプリのグロース支援実績があります。アプリのグロース戦略でお悩みの方は、ぜひ一度、株式会社ペンタゴンまでご相談ください。
株式会社ペンタゴンによるアプリのグロース実績
株式会社ペンタゴンでは、お客様や関係各所と一体となり、データに基づくアプリの成長支援を行っています。まず初めに「KPIツリー」の策定を行い、コンサルタント・デザイナー・クライアントを交えて最重要指標を明確にします。その上で、設定したKPIに基づき、UI/UXデザイナーと共に改善案を立案。リソースを考慮しつつ、数値インパクトの大きい施策から優先的に実施していきます。
筆者が支援しているアプリでは、ユーザー規模が大きいため、わずか1%の改善でも大きな成果につながります。実際に、約3ヶ月ごとの大規模な改修をベースに継続的な改善を重ね、ウィークリーアクティブユーザーを約3%向上させた事例もあります。こうした定量的な成果を蓄積しながら、アプリの持続的な成長を実現しています。
KPIツリーの作り方はこちらの記事をご覧ください。
アプリの成長に必須!『KPI ツリー』を作成する本当の意味とは?
アプリのグロースで見るべき6つの重要 KPI とは?
グロース戦略を立てる上で重要な指標をピックアップして解説します。
KPI① インストール数と CPA(顧客獲得コスト)
CPA(顧客獲得コスト)は、広告費用をインストール数で割った値で算出されます。持続可能な成長を実現するためには、CPA が LTV を下回る必要があります。業界標準では LTV/CAC 比率が 3:1 以上が推奨されており、4:1 以上は優れたビジネスモデルとされています。(参考:LTV:CAC Ratio | KPI example | Geckoboard)
例えば、LTV が 10,000 円のアプリの場合、CPA は 3,000-5,000 円以下に設定することで、健全な成長を維持できます。
KPI② 新規登録率
新規登録率は、インストール数に対する新規登録数の割合を示します。これは、ユーザーがアプリをインストールした後の最初の関門となる重要な指標です。
金融アプリでは本人確認が必要なため登録率が低くなる傾向があり、ゲームアプリでは気軽に始められるため登録率が高くなる傾向があります。ソーシャルログインやゲスト機能の提供により、登録のハードルを下げることが重要です。
KPI③ 継続率(リテンション)
継続率として、次のような指標を追っていきます。
◆継続率の指標
- Day1 継続率: 翌日もアプリを利用する割合
- Day7 継続率: 1 週間後も利用する割合
- Day30 継続率: 1 ヶ月後も利用する割合
◆ 業界別継続率の目安
| アプリ種類 | Day1 | Day7 | Day30 |
|---|---|---|---|
| ゲーム | 29% | 13% | 6% |
| EC | 19-24% | 10% | 5% |
| フィンテック | 30% | 18% | 9% |
| ヘルスケア | 24% | 9% | 7% |
| ソーシャル | 23% | - | 7% |
出典:Mobile App Retention Benchmarks By Industries 2025 | UXCam
KPI④ DAU/MAU 比率(アクティブ率)
- 定義: DAU ÷ MAU × 100
- 重要性: ユーザーのエンゲージメント深度を示す
- 目安: 20-40%(アプリ種類により変動)
Mixpanel 2024 Benchmarks Report によると、全業界平均の DAU/MAU 比率は 37% で、一般的に 20% 以上が優秀とされます。
KPI⑤ LTV(顧客生涯価値)
定義: ユーザーがアプリから生み出す総収益
計算例: ARPU ÷ チャーン率
重要性: 長期的な収益性とマーケティング投資判断の基準
※チャーン率とは、一定期間内にアプリを停止またはアンインストールしたユーザーの割合です。例えば、月次チャーン率が 5% の場合、毎月 5% のユーザーがアプリを停止していることを意味します。
KPI⑥ ROAS(広告費用対効果)
定義: 広告経由の収益 ÷ 広告費用
重要性: マーケティング投資の効率性を測定
目安: 300-500%以上(業界・フェーズにより変動)
参考:The Complete Guide to ROAS | Daasity によると、プラットフォーム別の ROAS 平均値は Amazon で約 300%、Facebook で 400-1000% となっています。ただし、ROAS は他の指標と合わせて総合的に評価することが重要です。
アプリ運用において KPI の正しい設定と測定は、グロース戦略の成否を左右します。詳細な KPI 設定については、以下の記事で詳しく解説しています。
» アプリ運用で見るべき KPI は?収益を上げる重要指標を解説
特に、DAU・WAU・MAU などの重要指標の理解と測定方法については、こちらの記事も参考にしてください。
» アプリの重要指標「DAU・WAU・MAU」とは?大企業で改善を行うプロが解説
アプリのグロースで実施すべき9つの施策
ステップに沿って、アプリに盛り込むべき施策の内容を具体的に紹介します。
◆アプリグロースで実施すべき9つの施策
| ユーザーの獲得につながる施策 | ・施策①ASO(アプリストア最適化) ・施策②デジタルマーケティング |
| ユーザーの維持につながる施策 | ・施策③価値体験の早期提供 ・施策④離脱防止の仕組み ・施策⑤ハビットループの構築 ・施策⑥エンゲージメント向上 ・施策⑦チャーン予防 |
| 収益の最大化につながる施策 | ・施策⑧マネタイゼーション最適化 ・施策⑨LTV 向上施策 |
施策① ASO(アプリストア最適化)
ASO は、アプリストア内での検索結果上位表示を目指す施策です。まず、ターゲットユーザーが検索する可能性の高いキーワードを選定し、アプリタイトルや説明文に自然に組み込みます。
◆例)アプリストアで「ダイエットアプリ」と検索

まず、ターゲットユーザーが検索する可能性の高いキーワードを選定し、アプリタイトルや説明文に自然に組み込みます。
アプリアイコンとスクリーンショットは、ユーザーの第一印象を決める重要な要素です。アイコンはシンプルで印象的なデザインにし、スクリーンショットは主要機能や価値を視覚的に伝える構成にします。アプリ説明文では、ユーザーの課題解決方法を明確に示し、レビューや評価の改善にも継続的に取り組みます。
施策② デジタルマーケティング
デジタルマーケティングでは、Facebook や Google 広告の最適化が基本となります。ターゲット設定を細かく調整し、広告クリエイティブを定期的に更新することで、CPA の改善を図ります。
インフルエンサーマーケティングでは、アプリのターゲット層にリーチ力のあるインフルエンサーを選定し、自然な形でアプリを紹介してもらいます。コンテンツマーケティングでは、ユーザーの課題解決に役立つ情報を発信し、リファラルプログラムではユーザー同士の紹介を促進する仕組みを構築します。
◆各施策の一覧表
| 施策 | 特徴・メリット |
|---|---|
| デジタル広告(Facebook / Google) | ターゲットを細かく設定でき、広告クリエイティブを改善しながらCPAを最適化できる。 短期間で成果を出しやすく、効果測定もしやすい。 |
| インフルエンサーマーケティング | ターゲット層に影響力のあるインフルエンサーが自然に紹介。 共感や信頼を得やすく、ブランド認知を一気に高められる。 |
| コンテンツマーケティング | ユーザーの課題を解決する情報を発信し、検索経由で長期的に集客できる。 広告費に依存せず、信頼性の高いリードを獲得できる。 |
| リファラルプログラム(紹介施策) | 既存ユーザーの紹介を促し、口コミで自然に拡散。 低コストで継続的に新規ユーザーを獲得できる。 |
マーケティング戦略を見据えたアプリ開発を行うことで、グロース施策の効果を最大化できます。開発段階からマーケティングを意識した設計について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
» マーケティングを見据えたアプリ開発を行うには?実践のポイント解説
施策③ 価値体験の早期提供
オンボーディングの成功は、ユーザーが早期にアプリの価値を実感できるかどうかにかかっています。チュートリアルは 3 ステップ以内に簡素化し、複雑な説明よりも実際の操作を通じて価値を体験してもらいます。
主要機能への誘導を強化することで、ユーザーが迷うことなくアプリの核となる価値にたどり着けるようにします。初期設定においては、ユーザーの属性や興味に基づいたパーソナライズを行い、「Aha! moment」(アプリの価値を実感する瞬間)を意図的に設計します。
施策④ 離脱防止の仕組み
離脱防止には、ユーザーの心理的負担を軽減する工夫が重要です。プログレスバーによる進捗可視化により、登録完了までの道のりを明確に示し、ユーザーの不安を軽減します。
情報入力は段階的に行い、一度に多くの情報を求めることを避けます。ソーシャルログインの提供により、登録の手間を大幅に削減し、ゲスト機能からの段階的登録により、まずはアプリを体験してもらってから本格的な登録に進んでもらう流れを作ります。
施策⑤ ハビットループの構築
ハビットループとは、ユーザーが無意識的にアプリを利用する習慣を形成する仕組みです。日常的な利用タイミングを創出するため、ユーザーの生活パターンに合わせた機能を提供します。例えば、朝の通勤時間や昼休みなど、特定の時間帯に利用価値の高いコンテンツを配信します。
リマインダー機能は、ユーザーの行動データを基に最適なタイミングで通知を送ります。習慣化をサポートする仕組みとして、連続利用日数の表示や、目標達成に向けた進捗状況の可視化を行います。これにより、ユーザーは自身の成長を実感し、継続利用への動機を維持できます。
施策⑥ エンゲージメント向上
エンゲージメント向上には、ユーザー一人ひとりに最適化された体験の提供が重要です。
◆ エンゲージメント向上のための施策
- パーソナライゼーション機能: ユーザーの行動履歴や嗜好に基づいたコンテンツ最適化
- ソーシャル要素: ユーザー同士の交流やコミュニティ形成の促進
- ゲーミフィケーション: 利用に対する報酬を提供
これらの施策の中でも、パーソナライゼーション機能は特に効果的で、ユーザーの過去の行動や嗜好に基づいてコンテンツを最適化することで、個人に最適化された体験を提供します。また、ソーシャル要素の追加では、ユーザー同士の交流が生まれることで、アプリを開く機会が生まれ利用促進につながります。
ちなみに、ゲーミフィケーションの導入は、実際に当社でも制作実績がありますが、ユーザーのエンゲージメント率を大きく改善することができます。
アプリの UI/UX デザインは、エンゲージメント向上に大きく影響を与えます。ユーザーが直感的に操作でき、魅力的な体験を提供するデザインは、継続利用率の向上に直結します。UI/UX デザインについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
» 【スマホアプリ企画者向け】UI/UX デザインの作り方 5 ステップ
施策⑦チャーン予防
チャーン予防は、ユーザーがアプリを使用しなくなる前に適切なタイミングでアプローチすることが重要です。
◆ 予防施策
- リエンゲージメントキャンペーン
- アプリ内メッセージの活用
- ユーザーフィードバックの収集と改善
リエンゲージメントキャンペーンとは、一定期間非アクティブになったユーザーに対して特別なオファーや新機能の紹介を行い、アプリへの関心を再び呼び起こします。
さらに、アプリ内メッセージを活用し、ユーザーがアプリを利用している最中に、適切なタイミングでヒントやオファーを表示することで、ユーザーに価値提供を行います。最後に、アプリストアレビューや評価機能を通じて得られた意見を継続的に分析し、ユーザーの不満を解消する改善を迅速に実施します。
施策⑧マネタイゼーション最適化
マネタイゼーションの最適化は、既存のユーザーからの収益を最大化するための重要な施策です。まず、価格戦略の最適化では、A/B テストを通じて最適な価格帯を見つけ、プランの細分化により、さまざまなユーザーニーズに対応します。
次に、アップセル・クロスセル施策では、ユーザーの利用状況や行動パターンを詳細に分析し、より高価なプランや関連サービスを適切なタイミングで提案します。特に重要なのは課金タイミングの最適化で、ユーザーがアプリの価値を十分に実感し、継続利用の意思を固めたタイミングで課金を促すことで、変換率の大幅な向上を図ることができます。
施策⑨LTV 向上施策
LTV 向上施策は、個々のユーザーがアプリから生み出す総価値を長期的に高めるための戦略的な取り組みです。具体的には、ロイヤリティプログラムを通じて継続的な利用や課金に対してポイントや特典を付与し、ユーザーの継続意欲を高めます。さらに、VIP ユーザー向け特典では、高額利用者に専用サービスや優先サポートを提供することで、優良顧客の満足度と忠誠度を向上させます。
これらと並行して、コミュニティ形成によりユーザー同士のつながりを構築し、アプリ内での社会的結びつきを強化することで離脱を効果的に防ぐことができます。最終的に、長期利用インセンティブとして利用期間に応じた割引や特典、達成賞などを段階的に提供することで、ユーザーの長期的なエンゲージメントと収益貢献を持続的に促進します。
アプリのグロースは開発会社とともに進めるべき
アプリのグロースを進める場合は、自社だけで考えるよりも、開発会社とともに開発段階のみならず運用段階でも一緒になって進めていくことがおすすめです。
多くの企業が「アプリを作ったら自社で運用する」と考えがちですが、実際にはグロースには専門的な知識と継続的な技術サポートが必要です。自社のみでグロースを進めようとして失敗するケースが後を絶たないため、ここでは具体的な課題と解決策をご紹介します。
アプリ開発をお考えの方、特にグロース戦略まで見据えた開発パートナーをお探しの方は、ぜひ一度株式会社ペンタゴンまでご相談ください。豊富な実績と専門知識で、お客様のアプリ成功をサポートいたします。
自社のみでグロースを進める場合の課題
課題① 技術的な制約
自社のみでグロースを進める場合、技術的な制約が大きな障壁となります。データ分析基盤の構築には、適切なデータ収集システムの設計、データベースの構築、分析ツールの導入など、高度な技術的知識が必要です。
A/B テスト機能の実装も同様に困難で、統計的に有意な結果を得るためのサンプルサイズの計算、テスト環境の構築、結果の正確な分析など、専門的なスキルが求められます。また、アプリのパフォーマンス改善やバグ修正、新機能開発のスピードが遅いと、市場の変化に対応できず、競合他社に後れを取ってしまいます。
アプリのグロースには高度な技術的基盤が必要です。ユーザー行動を詳細に分析するためのデータ収集機能、効果的な A/B テストを実行するための仕組み、リアルタイムでのパフォーマンス監視システムなど、専門的な技術スキルが求められます。自社内にこれらの技術力がない場合、グロース施策の実行に大きな制約が生じます。
具体的な問題例
- データ分析ツール(Google Analytics、Firebase)の設定ミスにより、正確な数値が取得できない
- A/B テストの統計的有意性を判断できず、間違った施策を継続してしまう
- アプリのクラッシュ率や読み込み速度の改善方法が分からない
- 新機能追加に数ヶ月かかり、市場の変化に対応できない
課題② 専門知識の不足
専門知識の不足は、グロース戦略の成否を大きく左右します。効果的な施策の選定には、業界特有のユーザー行動パターンや成功事例の理解が必要ですが、これらの情報は実際の運用経験なしには得られません。
データ分析においても、単に数値を見るだけでなく、その背景にある要因を正確に理解し、適切な改善策を導き出すスキルが必要です。業界ベンチマークとの比較ができないと、自社の立ち位置や改善の優先度を正しく判断できません。また、新しい技術やツールの導入時には、セキュリティやパフォーマンスへの影響を適切に判断する必要があります。
グロースハッキングには、マーケティング、データサイエンス、プロダクト開発の知識が総合的に必要です。どの施策が自社のアプリに適しているか、データからどのような洞察を得るべきか、競合他社と比べて自社の立ち位置はどうなのかといった判断には、豊富な経験と専門知識が不可欠です。
課題③ リソースの制約
リソースの制約は、多くの企業が直面する現実的な課題です。本業と並行してグロース業務を行う場合、どうしても片手間での対応となり、十分な時間と集中力を確保できません。
グロースは継続的な改善サイクルを回すことが重要ですが、限られたリソースでは定期的な分析、施策の企画・実行、効果測定を継続することが困難です。アプリのクラッシュやパフォーマンス問題が発生した際の緊急対応も遅れがちで、ユーザー体験の悪化を招きます。また、グロース業務と他の業務との優先順位調整も難しく、短期的な業務に押し切られてしまうことが多いです。
グロースは継続的な取り組みが必要ですが、本業と並行して行う場合、どうしても優先順位が下がりがちです。また、アプリのクラッシュやパフォーマンス問題が発生した際の緊急対応、新しい施策のテスト実行、データ分析レポートの作成など、多岐にわたる業務を限られたリソースで対応するのは困難です。
開発会社と連携する3つのメリット
メリット① 技術的なサポート
- 高度な分析機能の実装
- 迅速な機能改善・追加
- パフォーマンス最適化
- 最新技術の活用
開発会社との連携により、グロースに必要な技術的な基盤を確実に構築できます。ユーザー行動の詳細分析、コホート分析、ファネル分析などの高度な分析機能を実装し、データドリブンなグロース施策を実行できます。また、新しい施策をテストするための機能追加や、アプリのパフォーマンス改善も迅速に対応できます。
メリット② 専門的な知見の活用
- 業界ベンチマークとの比較
- 効果的な施策の提案
- データ分析の高度化
- 競合分析の実施
開発会社が蓄積している業界知識や他社の成功事例を活用できます。自社のアプリの KPI が業界平均と比べてどうなのか、どのような施策が効果的なのか、競合他社がどのような戦略を取っているのかといった情報を基に、より戦略的なグロース施策を立案できます。
メリット③ 継続的なパートナーシップ
- 長期的な成長戦略の立案
- 定期的なレビューと改善
- 緊急時の迅速な対応
- 技術トレンドへの対応
開発会社との長期的なパートナーシップにより、一時的な改善ではなく、継続的な成長を実現できます。定期的なレビュー会議でのデータ分析、新しい施策の提案、市場環境の変化に応じた戦略修正など、伴走型のサポートを受けることで、持続的なグロースが可能になります。
株式会社ペンタゴンが支援するアプリグロース支援
ここでは、当社におけるグロース支援の具体的な内容とアプローチをご紹介します。
支援① KPI ツリーの作成
まず最初に、グロース戦略の土台となるKPI ツリーを作成します。最終的なビジネス目標から逆算して各段階の重要指標を体系的に整理し、効果的な施策立案の基盤を構築します。KPI ツリーにより、最終的なビジネス目標と日々の施策を直結させ、全ての取り組みが成果につながる仕組みを設計します。
KPI ツリーの重要性と具体的な構築方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
» アプリの成長に必須!『KPI ツリー』を作成する本当の意味とは?
支援② データ分析体制の構築
- Google Analytics、Firebase、Mixpanel の導入・設定
- ファネル分析とコホート分析の実装
- クラッシュ監視体制の構築
- カスタムダッシュボードの構築
KPI ツリーに基づき、必要な指標を正確に計測できるデータ分析体制を構築します。Google Analytics、Firebase、Mixpanel などの分析ツールを、お客様のビジネスモデルに合わせてカスタマイズして導入・設定します。ファネル分析とコホート分析の実装により、ユーザーの行動パターンや離脱ポイントを詳細に把握し、クラッシュ監視体制によりアプリの安定性を継続的に監視します。
支援③ 戦略の立案と実行
- ユーザー行動データの詳細分析
- 施策の立案と優先度の決定
KPI ツリーをもとに「この施策がこの数値に影響を与える」といった仮説を立てつつ、施策の優先度を決めていきます。この施策の優先度を決めるときは、コストと想定効果の 2 軸で考えます。例えば、「プッシュ通知の最適化により継続率を 5%改善できる」「実装コストは中程度」といった形で各施策を評価し、最も効果対コスト比の高い施策から優先的に実行します。
支援④継続的な改善サポート
- 月次レビュー会議の実施
- A/B テストの設計・実行・分析
- 新機能の企画・開発
- パフォーマンス最適化
グロースは継続的な改善の積み重ねです。当社では月次のレビュー会議を通じて、前月の施策効果を詳細に分析し、次月の改善計画を立案します。A/B テストの設計から結果分析まで一貫してサポートし、統計的に有意な結果に基づいた改善を実行します。また、データ分析の結果に基づいて新機能の企画・開発も行い、ユーザー体験の継続的な向上を図ります。
アプリの改善・グロースに効果的なツールについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
» アプリの改善・グロースにおすすめのツール6選【2025 年版】
競合分析の重要性とその実践方法についても解説しています。
» アプリ開発の競合分析、フレームワークと効果的なツール 3 選
グロース戦略を始める前にチェックすべきこと
グロース戦略を検討する際、「何から始めればいいの?」「自社でできることと専門家に依頼すべきことの境界線は?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、グロース戦略を始める前に確認すべき重要なポイントをチェックリスト形式でご紹介します。このチェックリストを使って、自社の現状を把握し、最適なアプローチを選択してください。
グロース準備チェックリスト
基础データの整備状況
▢ アプリ内のユーザー行動データが収集できている
→ Google Analytics や Firebase などの解析ツールが正しく設定されているか確認
▢ 基本的な KPI(DAU、MAU、継続率など)が測定できている
→ 数値が正しく取得できていない場合は、まず計測環境の整備が必要
▢ ユーザーフィードバックの収集ルートが確立されている
→ アプリストアレビュー、サポート問い合わせ、アプリ内フィードバック機能など
技術的基盤の確認
▢A/B テストが実施できる環境が整っている
→ 施策の効果を正確に測定するために不可欠
▢ 新機能追加や改修が迅速に対応できる体制がある
→ グロースにはスピードが重要、数週間で改善できるかがポイント
▢ アプリのパフォーマンス最適化が対応可能
→ 表示速度やクラッシュ率の改善はユーザー体験に直結
組織体制の整備
▢ グロース施策の実行を担当するチームが明確になっている
→ マーケティング担当、開発担当、データ分析担当などの役割分担
▢ 定期的な成果検討会議の日程が組まれている
→ 週次または月次での定期レビューが重要
▢ 必要に応じて外部の専門家に相談できる体制がある
→ 内部リソースだけでは限界があるため、必要時のサポート体制を確保
チェックリストの活用方法
上記のチェックリストで、7 項目以上にチェックがついた場合は、自社主導でのグロース戦略開始が可能です。
5-6 項目の場合は、部分的な外部サポートを活用しながら進めることをおすすめします。
4 項目以下の場合は、まず基盤整備から始めることが重要です。この場合は、経験豊富な開発会社とのパートナーシップが最も効果的です。
まとめ
アプリのグロース戦略は、単発の施策ではなく継続的な改善サイクルを回すことが重要です。
◆グロース成功のポイント
- データドリブンな意思決定: 仮説ではなくデータに基づく施策実行
- ユーザー中心の設計: ユーザー体験を最優先に考えた改善
- 長期的な視点: 短期的な成果だけでなく LTV 最大化を目指す
- 継続的な改善: PDCA サイクルを高速で回す体制構築
- 専門パートナーとの連携: 技術・ノウハウ不足を補う外部連携
株式会社ペンタゴンでは、アプリの開発段階からグロース戦略を見据えた設計を行い、リリース後も継続的な成長をサポートしています。データ分析基盤の構築から具体的な施策実行まで、包括的なグロース支援をご提供いたします。
今回ご紹介した「アプリグロース戦略の方法」を参考にして、アプリの成長戦略を検討しましょう。もし「自社アプリのグロース戦略を立てたい」「継続率や LTV を改善したい」などお考えでしたら、グロースを見据えた開発パートナーとして、株式会社ペンタゴンをご検討ください。
下記からもお問い合わせできますので、お気軽にご相談ください!