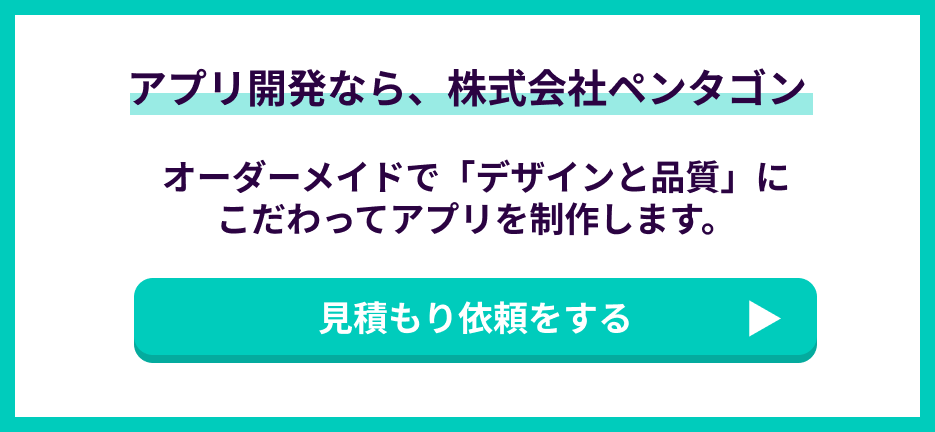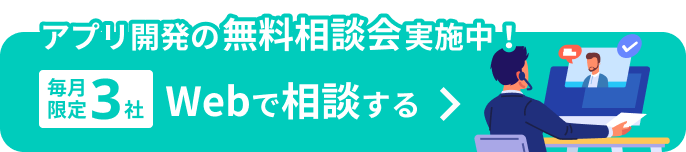【初心者向け】アプリ開発を初めて発注する時の基本ステップ

「アプリを作りたいけれど、何から決めればいいのか分からない」「そもそも、どのくらい費用がかかるのかイメージが湧かない」 アプリ開発が初めての方からは、このようなご相談を非常によくいただきます。
本記事では、アプリ開発会社「株式会社ペンタゴン」で多くのプロジェクトに関わってきた筆者が、アプリ開発を初めて発注する初心者向けに、実践的なステップと考え方を分かりやすく解説します。
◆初めてアプリ開発を発注する時のポイント
- ① 作るアプリを言語化する
「誰に・どんな価値を・なぜ届けるのか」を明確にする - ② アプリの種類と開発方法を選ぶ
ネイティブ/クロスプラットフォーム/Web、スクラッチ/パッケージ/ノーコードの違いを理解する - ③ 費用相場と依頼先の選び方を知る
自社の予算感と目的に合った開発会社を選定する
これらのポイントを一つずつ押さえていけば、「アプリ開発の初心者」であっても、自信を持って発注の準備を進めていけます。順を追って見ていきましょう。
最初の一歩:「作るアプリ」を明確にする
アプリ開発を初めて発注するとき、最初に行うべきことは「どんなアプリを作るのか」を自社内で言語化することです。
ここが曖昧なまま進めてしまうと、機能が増え続けてしまったり、開発会社との認識ズレが何度も起きてしまったりします。
ポイント①:ユーザーにどんなメリットを届けるのか
まずは、「誰の」「どんな課題を」「どう解決するアプリなのか」を具体的に書き出してみましょう。
- どんなユーザーに使ってほしいのか(例:既存顧客、店舗のリピート客、社内の営業メンバー 等)
- そのユーザーは、今どんなことに困っているのか
- アプリを通じて、どのようなメリットを提供したいのか
例えば「店舗の予約アプリ」を作りたい場合でも、
- 予約の電話が多すぎて、スタッフの手を止めてしまう
- 当日キャンセル・無断キャンセルを減らしたい
- 常連のお客様にだけ、特別なクーポンを配信したい
といった課題・目的を具体的に整理することで、実装すべき機能や、優先度が自然と見えてきます。
このように、ユーザー視点でのメリットを書き出しておくことで、「その機能は本当に必要か?」という判断がしやすくなり、無駄な機能を作りすぎるリスクを減らせます。
実際にアプリ開発の企画をまとめる際には、以下の記事も参考にしてください。
【テンプレ無料】プロが教える「アプリ開発企画書」の9つのポイント
ポイント②:ビジネスとしての目的と数値目標を決める
アプリは「作ること」がゴールではなく、ビジネス課題を解決する手段です。
そのため、ユーザーメリットと合わせて、「ビジネス側のゴール」も必ずセットで決めておきましょう。
- 予約の電話本数を◯%削減したい
- 来店回数を平均月◯回→◯回に増やしたい
- 問い合わせ対応にかかる時間を月◯時間削減したい
こうした数値目標(KPI)があると、開発会社としても「どこに時間と予算をかけるべきか」を提案しやすくなりますし、リリース後にアプリの成果を検証する際の指標にもなります。
ポイント③:最初のリリースで「やらないこと」も決める
初心者の方ほど、「あれもできたら便利そう」「せっかくだからこの機能も」と、機能を盛り込みすぎてしまう傾向があります。
しかし、すべてを一度に実装しようとすると、費用も期間も膨らみ、リリースがどんどん先延ばしになってしまいます。
そこでおすすめなのが、「最初のリリースで必須な機能」と「後から追加してもいい機能」を分けることです。
- 必須機能:この機能がなければアプリとして成立しない
- 優先度中:あると便利だが、後からでも追加できる
- 優先度低:将来構想として頭の片隅に置いておく
弊社(株式会社ペンタゴン)でも、要件定義の段階でこうした優先度付けを行い、「スモールスタート → 改善」という流れを前提に設計することで、開発リスクを下げるようにしています。
最初から完璧を目指すのではなく、「まずは核となる価値に集中する」ことが、初心者にとっての最重要ポイントです。
開発するアプリの種類を決める
作りたいアプリの目的やユーザー像が見えてきたら、次は「どの種類のアプリにするか」を決めます。
代表的な種類は、以下の3つです。
◆アプリの3つの種類
- ネイティブアプリ(iOS / Android 向け)
- クロスプラットフォームアプリ(Flutter 等)
- Webアプリ(ブラウザ上で動作するアプリ)
それぞれの特徴と、初心者が選ぶときの基準を整理しておきましょう。
ネイティブアプリ:高いユーザー体験が必要な場合に有力
ネイティブアプリは、iOS・Android それぞれのOS向けに専用の言語で開発するタイプです。
メリット①:処理速度が速く、動作がなめらか
メリット②:プッシュ通知やカメラ、GPSなど、スマホの機能をフル活用しやすい
メリット③:アプリストアでの露出が見込める
一方で、iOSとAndroidで別々に開発する必要があるため、費用が高くなりがちという側面があります。一般的にも、Webアプリに比べるとネイティブアプリは開発コストが高くなります。
「ユーザー体験を徹底的に磨きたい」「社外向けのブランディングも兼ねたい」ようなケースでは、ネイティブアプリが有力候補になります。
クロスプラットフォームアプリ:コストと品質のバランス重視
近年主流となってきているのが、Flutter(フラッター) などのクロスプラットフォーム技術を使ったハイブリッドアプリです。
1つのコードベースから iOS / Android 両方のアプリを同時に開発できるため、工数やコストを抑えやすいという特徴があります。
メリット①:1つの開発でiOS / Android両対応できるため、コストを抑えやすい
メリット②:ネイティブアプリに近い操作感・デザインが実現しやすい
メリット③:保守・アップデートがシンプルになりやすい
弊社でも、Flutter を用いたクロスプラットフォーム開発を多く手掛けており、品質と開発スピードを両立しやすい点を評価しています。
「予算は限られているが、きちんとしたアプリ体験を提供したい」という初心者の方には、まず検討していただきたい選択肢です。
なお、Flutterは様々な有名アプリでも採用されています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
Flutterアプリの国内事例12選!大手のFlutter移行も紹介
Webアプリ:まずは小さく試したい場合に有効
Webアプリは、ブラウザ上で動作するアプリケーションです。
URLにアクセスするだけで利用できるため、インストール不要であることが特徴です。
メリット①:比較的低コストで開発しやすい
メリット②:iOS / Android といったOSの違いを意識せずに提供できる
メリット③:既存のWebサービスとの連携がしやすい
一方で、アプリストアからのインストールではないため、「アプリをインストールする」という体験を期待しているユーザーには届きにくい側面もあります。
「まずは社内向けツールとして試したい」「PoC(概念実証)として小さく始めたい」といったケースでは、Webアプリからスタートし、手応えがあればネイティブ/ハイブリッドに拡張する、という進め方も有効です。
アプリの種類について、より詳しい比較は以下の記事をご覧ください。
ネイティブアプリとは?Webアプリ・ハイブリッド・PWAと比較
アプリの開発方法を選ぶ:3つのパターン
アプリの種類が決まったら、次は「どのような開発方法を取るか」を考えます。
大きく分けると、次の3パターンがあります。
- 開発方法①:フルスクラッチ開発
- 開発方法②:パッケージ / テンプレート活用
- 開発方法③:ノーコード+部分的カスタム
それぞれの特徴と、初心者が選ぶときのポイントを見ていきましょう。
開発方法①:フルスクラッチ開発
フルスクラッチ開発は、その名の通りゼロからオリジナルのアプリを設計・開発していく方法です。
メリット①:要件に合わせて自由度の高い設計ができる
メリット②:細かな仕様まで自社に最適化しやすい
メリット③:将来的な拡張性を柔軟に持たせられる
その分、開発工数が多く、費用も期間も大きくなりやすいのが難点です。一般的にも、フルスクラッチのアプリ開発では、最低限の機能構成でも数百万円規模、機能が増えると1,000万円以上になるケースも珍しくありません。
「自社独自のコンセプトを実現する」「既存システムとの複雑な連携が必須」といった場合には有力な選択肢です。
開発方法②:パッケージ / テンプレート活用
次に、既存のパッケージやテンプレートをベースにカスタマイズしていく開発方法です。
メリット①:基本機能が揃っているため、費用と期間を抑えやすい
メリット②:よくある業務や業界ニーズに最適化されたテンプレートが多い
メリット③:フルスクラッチに比べて、仕様検討の負荷が軽くなりやすい
コスト感としては、スクラッチ開発よりも低く、規模にもよりますが、数百万円程度からスタートできるケースも少なくありません。
ただし、「テンプレートの範囲を超えた独自機能」が増えてくると、結果的にカスタマイズ費用が大きくなり、スクラッチとあまり変わらない、というケースもあります。
「自社の要望をどこまでテンプレートに寄せられるか」が、費用を抑えるための重要なポイントです。
開発方法③:ノーコード+部分的カスタム
近年増えているのが、ノーコードツールを活用したアプリ開発です。
画面のレイアウトや簡単なロジックであれば、プログラミングなしでも構築できるプラットフォームが多数登場しています。
メリット①:初期費用を大きく抑えられる(数十万円〜数百万円程度の事例も)
メリット②:要件がシンプルな場合、短期間で形にできる
メリット③:PoC(概念実証)として「まず試してみる」用途に向いている
一方で、複雑な業務ロジックや大規模トラフィックには向かないケースも多く、カスタマイズの限界もあります。そこで、最近は「ノーコードでプロトタイプを作り、手応えを見てから本格的なスクラッチ開発に移行する」といった二段階戦略もよく採用されています。予算が確保できない場合は、ノーコードがおすすめです。
初心者の方がいきなり大きな投資をするのが不安な場合、このような「まずは小さく試す」アプローチも検討してみると良いでしょう。
アプリ開発の費用相場をざっくり掴む
ここまでで、「作るアプリのイメージ」「アプリの種類」「開発方法」が少し見えてきたと思います。
次に気になるのが、「結局いくらくらいかかるのか?」という費用相場です。
費用の全体像:開発費+運用費
アプリ開発にかかる費用は、大きく分けて次の2つのカテゴリがあります。
- 開発費(最初にかかる一括の費用)
- 運用・保守費(リリース後に継続的にかかる費用)
当社は、2023年2月インターネット調査を実施し、アプリ開発に携わったことがある354名にアンケート調査を行いました。その結果、アプリ開発にかかった費用はおおよそ半数が300万円以上と回答しました。また、大規模な開発には2,000万円以上かかる場合もあることが明らかになりました。
もちろん、機能の多さや開発方法によっては、50万円未満の小規模なものから、1,000万円を超える大規模案件まで幅はあります。
重要なのは、「自社のアプリがどの規模に当てはまりそうか」をざっくり把握しておくことです。
規模別のイメージ
細かな数字はプロジェクトごとに大きく変わりますが、初心者の方でもイメージしやすいように、規模ごとのざっくりしたイメージを整理しておきます。
- シンプルなアプリ:300〜500万円
画面数が少なく、基本的な機能構成のアプリ(例:簡易な社内ツール、クーポン配布アプリ等) - 中規模アプリ:500〜1,500万円
ログイン機能やユーザー管理、通知、外部サービス連携などを含む業務・店舗アプリ - 高度/複雑なアプリ:1,500〜3,000万円
マッチング、決済機能を備えた多数のユーザー向けサービス、高度なセキュリティが必要なアプリ - エンタープライズ(大企業向け):3,000〜5,000万円
大規模トラフィックに対応し、複雑な業務フローや既存システムとの統合が必要なアプリ
あくまで目安ではありますが、「自社の構想はどのレンジに近そうか?」をイメージしておくと、開発会社との初回相談もスムーズになります。
より詳しい費用相場については、以下の記事で実際の見積もりを公開しながら解説しています。
アプリ開発初心者のための依頼先の選び方
最後に、アプリ開発を初めて発注する方にとって非常に重要な、**「開発会社の選び方」**について整理します。
弊社にも、「他社で安さだけを基準に発注した結果、半年以上プロジェクトが止まってしまった」「2年以上遅延して未リリースのままになっている」といったご相談が多く寄せられます。
こうした事態を防ぐためにも、初心者の方ほど、以下のポイントを意識して依頼先を選んでいただきたいと考えています。
ポイント①:企画段階から相談できるか
初心者の方にとって最も大切なのは、「仕様書を出してくれれば作ります」というスタンスではなく、「何を作るべきか」から一緒に考えてくれる会社かどうかです。
- アプリの目的やビジネスゴールについてヒアリングしてくれるか
- 優先度付けや段階的なリリース案を、一緒に検討してくれるか
- 「その機能は本当に今必要か?」といった視点で提案してくれるか
こうしたコミュニケーションができる開発会社は、単なる「下請け」ではなく、パートナーとして伴走してくれる可能性が高いと言えます。
ポイント②:見積もりの内訳と前提をきちんと説明してくれるか
見積書は、金額の大小だけでなく、「どの作業にどれだけ工数を割いているか」が重要です。
- 要件定義や設計にどの程度の時間を割いているか
- テストや品質保証の工程はどう組み込まれているか
- アプリストア申請や審査対応の費用が含まれているか
これらを丁寧に説明してくれる会社は、プロジェクト全体のリスクもきちんと見据えているケースが多いです。
逆に、「とにかく安くできます」「詳細はやりながら決めましょう」といったスタンスの場合、後から追加費用が膨らんだり、品質面でトラブルになるリスクが高まります。
ポイント③:品質管理・テスト体制が明確か
アプリは、リリースして終わりではありません。
バグが多かったり、使いづらさが目立つと、ユーザーの離脱や低評価レビューにつながってしまいます。
- テストはどのような体制で行っているか(開発者以外の第三者テストがあるか)
- 不具合が発生した際の対応フローはどうなっているか
- リリース後の改善・アップデート計画まで一緒に考えてくれるか
こうした点を確認しておくことで、「とりあえず動くものができたけれど、使ってもらえないアプリ」になってしまうリスクを避けやすくなります。
よくあるNGな選び方
最後に、初心者の方がやりがちなNGパターンも触れておきます。
- NG①:「最安値の会社」を選んでしまう
→ 品質管理や要件定義の工数が十分に確保されておらず、結果的に作り直しになるケースも多いです。 - NG②:丸投げしてしまう
→ 自社内で目的や優先順位が整理されていないと、途中から「思っていたのと違う」という事態になりがちです。 - NG③:実績や得意分野を見ずに選んでしまう
→ 自社の業界やアプリのタイプに近い実績を持っているかどうかは、重要な判断材料になります。
初心者だからこそ、「価格だけ」で決めるのではなく、「一緒に考えてくれるか」「プロジェクト全体を見てくれるか」といった観点を重視して、信頼できるパートナーを選んでいただきたいと思います。
まとめ:最初の一歩を丁寧に踏み出せば、初心者でも怖くない
ここまで、アプリ開発を初めて発注する初心者向けに、
- ① 作るアプリの目的やユーザー価値を言語化する
- ② アプリの種類(ネイティブ/ハイブリッド/Web)と開発方法を選ぶ
- ③ 費用相場と依頼先の選び方を理解する
という流れで解説してきました。
アプリ開発は専門用語も多く、最初は難しく感じられるかもしれません。
しかし、「なぜ作るのか」「誰にどんな価値を届けたいのか」という軸さえブレなければ、細かな技術的な部分は、信頼できる開発会社と一緒に詰めていくことができます。
この記事で紹介した考え方をベースに、自社のアプリ構想を一度書き出してみるところから始めてみてください。
整理された情報があればあるほど、開発会社との初回相談もスムーズになり、結果として費用面・品質面の両方で満足度の高いプロジェクトにつながります。
今回ご紹介したアプリ開発の進め方を参考に、アプリ開発企画を進めていきましょう。もし「自社の事業向けアプリを作りたいけど、実際にアプリ開発の費用はどれくらいになるのか?」「アプリ開発の外注を検討していて、一度相談したい」などお考えでしたら、アプリ開発会社の株式会社ペンタゴンをご検討ください。
株式会社ペンタゴンの開発実績については、こちらをご覧ください。
» 株式会社ペンタゴンの開発実績を見る
下記よりお問い合わせできますので、お気軽にご相談ください!