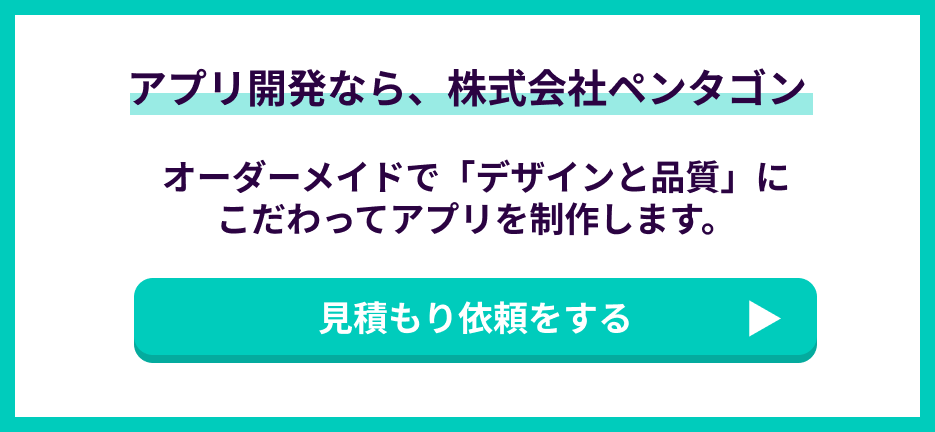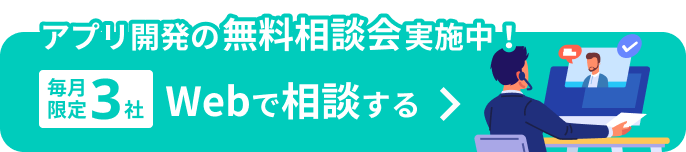AIでアプリは簡単に作れる?甘くない現実と外注の強みを解説

生成AIやノーコードツールの普及により、「もうアプリ開発はAIに任せればいいのでは?」という声を聞くことが増えてきました。ChatGPTにコードを書かせたり、ノーコードツールで画面を組み立てたりすれば、これまでエンジニアに依頼していたようなアプリも、自社だけで作れてしまいそうに見えます。
しかし、実務の現場でアプリ開発に10年以上携わっている立場から言うと、「AIでアプリは簡単に作れる」というのは半分だけ正しく、半分はとても危ういのです。
本記事では、アプリ開発会社「株式会社ペンタゴン」でエンジニアを務める筆者が、AI×ノーコードでできること・限界・そして外注(プロに依頼)する強みを、できるだけわかりやすく整理して解説します。
まず最初に、本記事のポイントを3つにまとめておきます。
- ① AI/ノーコードで「どの程度のアプリ」なら作れるのか がわかる
- ② AI開発の甘くない現実(限界とリスク) を理解できる
- ③ どんなアプリはプロに外注すべきか、その判断基準 を持てるようになる
この記事を読み終えるころには、
「うちのアプリ構想はAIで試すべきか? それとも最初から開発会社に相談すべきか?」
を冷静に判断できるはずです。
AI×ノーコードでアプリ開発をする3つの代表的な方法
まずは、「AIを使ってアプリを作る」と言ったときに、具体的にどんな方法があるのかを整理しておきましょう。大きく分けると、次の3つのパターンがあります。
方法①AIにコードを書かせる(バイブコーディング的な使い方)
ChatGPTのような生成AIに対して、
「〇〇ができるiOSアプリのサンプルコードを書いて」
とプロンプトを送ると、実際に動くコードが返ってきます。
これをコピペしたり、一部修正したりしながらアプリを組み立てていくスタイルです。
- 画面遷移やフォーム入力などの定型的な処理
- API連携のサンプルコード
- ちょっとした不具合の修正案
などは、AIに尋ねることでかなりの部分を自動化できます。エンジニアであれば、「ゼロから調べて書くよりも、AIの提案をベースに素早く組み立てる」 という使い方で、生産性を大きく上げられます。
一方で、プログラミング未経験の方がこの方法で1からアプリを完成させるのは、ハードルが高いのが現実です。なぜなら、
- AIが出力したコードが本当に正しいかどうかを見極める力
- エラーが出たときに原因を切り分ける力
がどうしても必要になるからです。
方法②ノーコードツールで画面とデータを組み立てる
次に、Bubble や Glide、Adalo、FlutterFlow などのノーコード/ローコードツールを使う方法です。
ドラッグ&ドロップで画面を配置し、ボタンとデータベースをつなげるだけで、ログイン機能や一覧画面などを構築できます。
ノーコードツールのメリットとしてよく挙げられるのは、
- メリット①:コードを書かずにアプリっぽいものを作れる
- メリット②:開発スピードが速い(小さなものなら数日〜数週間)
- メリット③:試しに作ってみるハードルが低い
といった点です。
最近は、これらのノーコードツールの中にも AI アシスタントが組み込まれており、「この画面に必要なロジックを作って」と指示すると、ある程度自動で設定してくれるものも増えてきました。
方法③AI搭載のアプリビルダーを使う
最近増えてきているのが、「テキストで要件を入力するとテンプレートアプリを生成してくれる」タイプのサービスです。
- 「タスク管理アプリを作りたい」
- 「店舗予約アプリを作りたい」
といった要望を入力すると、画面構成や項目がある程度整った状態でアプリが生成され、そこから項目名やデザインを自社用に調整していく、という使い方になります。
このように、「AI×ノーコード」を組み合わせることで、以前よりも圧倒的に低コスト・短納期で「とりあえず動くアプリ」を作る手段は確かに手に入りました。
では、その「とりあえず動くアプリ」は、どこまで実用に耐えられるのでしょうか。次の章で解説します。
AI×ノーコードで「十分」なケースと、そのリアル
現場の感覚として、AI×ノーコードで十分に実用レベルに持っていきやすいケースは、ある程度共通しています。代表的なものを挙げると、次のようなパターンです。
◆AIとノーコードが良いケース
- ケース①:社内のみで使う業務アプリ
例)特定部署だけが使う在庫管理や、簡易な申請フロー管理 - ケース②:プロトタイプ(試作品)としてのアプリ
例)新規事業の仮説検証のために、ユーザーテストで使う試作版 - ケース③:シンプルな機能だけを実現するアプリ
例)フォーム入力してデータを一覧で確認するだけ、といった構成
こうしたケースでは、
- ユーザー数がそこまで多くない
- 機能がシンプルで、複雑な計算やリアルタイム通信がない
- 万が一不具合があっても、大きな法的リスクにつながりにくい
といった条件が揃うため、AI×ノーコードでも十分に実用的なアプリを構築できます。
特に、新規事業のアイデア検証においては、
- まずはノーコードでプロトタイプを作る
- 実際のユーザーに触ってもらって反応を確認する
- 手応えがあれば、改めて本格的な開発を行う
というステップを踏むのは、とても合理的なアプローチです。
ただし、ここで勘違いしてはいけないのが、
「プロトタイプが動く = 本番運用に耐えられるアプリができた」ではない
という点です。
AIを使ったアプリ開発の「甘くない現実」と限界
ここからが本題です。
AI×ノーコードでアプリ開発を行うとき、現場でよく問題になる「甘くない現実」は、主に次の4つです。
限界①作った人しか触れない「ブラックボックス化」
ノーコードで組んだ設定や、AIが出力したコードは、一見シンプルに見えても、
- どの画面がどのデータベースにつながっているのか
- どのルールがどのトリガーで動いているのか
- どこまでがAIの提案で、どこからが手作業の修正なのか
といった「全体像」が分かりづらくなりがちです。
その結果、
- 担当者が退職・異動した瞬間、誰も中身を理解できないアプリが出来上がる
- バグ報告が来ても、なぜその挙動になっているのか追えない
- 仕様変更したいのに、どこを触ればいいか分からず、結局作り直しになる
といったケースが非常によく起こります。
特にノーコードツールは、「画面上で設定を積み上げていく」スタイルのため、履歴や意図がドキュメントとして残りにくいという問題もあります。
限界②ツールの制約・仕様変更に振り回される
ノーコード/ローコードツールは、プラットフォーム側が用意してくれた部品を組み合わせてアプリを構築します。そのため、
- 「あと一歩、ここだけ変えたい」が実現できない
- ある日突然の仕様変更で、今まで使えていた機能の挙動が変わる
- プラン改定で、必要な機能が上位プラン限定になる
といった問題が発生することがあります。
小さな社内ツールであれば割り切れますが、外部ユーザー向けの本格的なアプリでこれが起きると、ビジネスへの影響は無視できません。
限界③セキュリティ・パフォーマンス・法令対応の壁
ビジネスの中核となるアプリになるほど、次のような観点が重要になります。
- 個人情報や決済情報を扱う場合のセキュリティ要件
- 数千〜数万ユーザーが同時接続しても耐えられるパフォーマンス設計
- 特定商取引法、電気通信事業法、利用規約・プライバシーポリシーなどの法令対応
AIやノーコードツールは、便利な一方で「中身のインフラや実装を細かくコントロールしにくい」ため、これらの要件をきちんと満たせるかどうかを判断するのが難しいという課題があります。
限界④AIが出したコードの“間違い”に気付けない
AIにコードを書かせるパターンでは、
- 一見動いているように見えるが、例外ケースで落ちる
- セキュリティ的に危険な書き方が混ざっている
- 将来的な拡張や保守を考えていない「場当たり的な実装」になっている
といったことが珍しくありません。
エンジニアであれば、AIが出したコードをレビューして危険な部分を手直しできますが、プログラミング未経験の状態でAI任せにしてしまうと、「動いているからOK」と判断してしまい、後から大きな問題になる可能性があります。
「簡単に作れるものは、簡単に真似される」という現実
AIやノーコードでアプリが簡単に作れるということは、「同じレベルのアプリなら、他社も簡単に作れる」ということでもあります。
つまり、
- テンプレート通りの画面構成
- ありきたりな機能セット
- オリジナリティの薄いUI/UX
のアプリは、差別化が極めて難しく、すぐに代替されてしまうということです。
アプリをビジネスとして成功させるためには、
- 独自のビジネスモデルや料金体系
- 利用シーンに最適化された、使いやすい導線設計
- ユーザーのインサイトを踏まえた、細かな体験設計
といった「独自性」が何より重要です。
AIやノーコードは強力な道具ですが、「独自性のある価値提案」や「ユーザー体験の細かな設計」そのものを自動で生み出してくれるわけではありません。
ここは、ビジネスとユーザーを深く理解している人間が、時間をかけて磨き込む必要があります。
どんなアプリはプロに外注すべきか?判断の目安
では、どのラインを超えたら「AI×ノーコードだけで進めるのは危険」で、「プロへの外注を検討すべき」と言えるのでしょうか。目安として、次のような条件が1つでも当てはまる場合は、開発会社への相談を強くおすすめします。
外注を検討すべきケースの例
- 条件①:自社の売上・利益の柱になるアプリにしたい
→ サービスの根幹を担うシステムを、ノーコード任せにするのはリスクが高いです。 - 条件②:数千人〜数万人以上のユーザー利用を想定している
→ パフォーマンスやスケーラビリティを考えた設計が必要になります。 - 条件③:決済・個人情報・ヘルスケア情報など、機微なデータを扱う
→ セキュリティ要件や法令対応を満たすために、専門知識が欠かせません。 - 条件④:競合が多い市場で、アプリの独自性が勝負の鍵になる
→ テンプレートではなく、UX・機能設計での差別化が不可欠です。 - 条件⑤:3〜5年以上の長期運用を前提としている
→ アップデートや仕様変更に耐えられるアーキテクチャ設計が重要です。 - 条件⑥:社内にエンジニアがいない/アプリ開発の経験者がいない
→ 仕様の整理から品質管理まで、プロの伴走がないとプロジェクトが迷走しがちです。
こうした条件に当てはまる場合、「AI/ノーコードで簡単に作れるから自社だけでやろう」という判断は、短期的には安く見えて、長期的には高くつく可能性が高いと言えます。
AIか外注か、ではなく「AI×プロ」のハイブリッドが最適解
ここまで読んでいただくと、
「じゃあAI開発はダメで、全部外注したほうがいいの?」
と思われるかもしれませんが、AIやノーコードは、上手に使えば、プロの開発とも非常に相性が良い道具です。
例えば、株式会社ペンタゴンでは、次のような形でAIを活用しています。
- 企画・要件定義フェーズで
→ AIにアイデア出しや画面ラフの生成を手伝わせ、検討スピードを上げる - 設計・開発フェーズで
→ テスト観点の洗い出しや、ユニットテストコードの叩き台生成など、品質向上のための補助ツールとして活用 - プロトタイプ作成フェーズで
→ ノーコードやAIツールで素早くプロトタイプを作り、本番実装前にユーザーの反応を確認
このように、
- 「発想や検証のスピードアップ」はAI/ノーコード
- 「本番運用を見据えた設計・実装・品質保証」はプロのエンジニア
と役割分担することで、開発スピードと品質の両方を追求することが可能になります。
「AIで簡単に作れるアプリ」と「本気で作るアプリ」を切り分けよう
「バイブコーディング」的にAIにコードを書かせたり、ノーコードツールを使うのは、アプリづくりの入り口としてはとても良い選択肢です。ただしそれは、あくまで「試してみる」「イメージを形にしてみる」ための手段であり、長期的にビジネスを支えるプロダクトを作るフェーズでは、やはり設計・品質・運用まで考えられるプロの力が欠かせません。
簡単に作れるということは、他社も簡単に同じようなものを作れるということです。
だからこそ、アプリで成功するうえで最も重要なのは、「誰にも真似できない独自性」をどう作り込むかだと、私たちは考えています。
この記事でご紹介した内容を参考に、自社アプリの開発方針を見直してみてはいかがでしょうか。
今回ご紹介したAI活用と外注の考え方を踏まえ、「どこまでを自社で試し、どこからをプロに任せるか」という線引きを検討してみてください。
もし「AIやノーコードも気になっているが、ビジネスとして本気で使えるアプリを作りたい」「予算をかけてしっかりと良いものを作りたい」とお考えでしたら、アプリ開発会社の株式会社ペンタゴンまでぜひご相談ください
株式会社ペンタゴンの開発実績については、こちらをご覧ください。
» 株式会社ペンタゴンの開発実績を見る
下記よりお問い合わせできますので、お気軽にご相談ください!